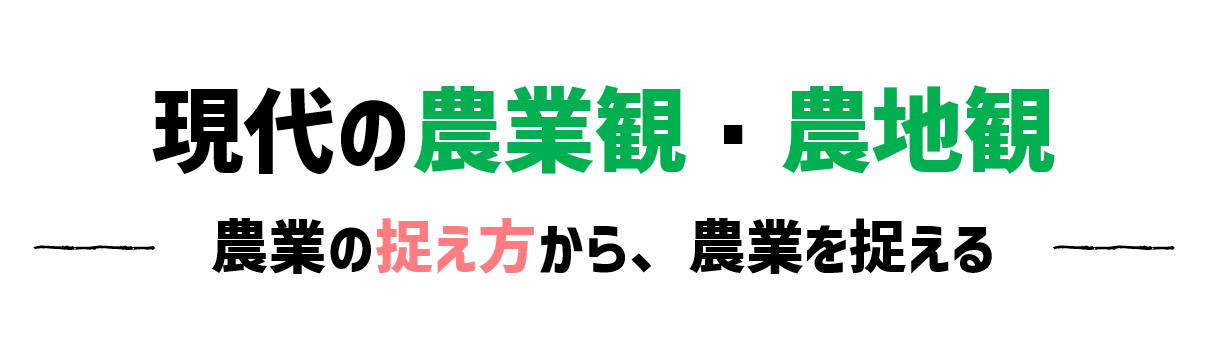近藤 正治 氏
1934年生まれ。
有限会社藤原ファーム代表取締役。
1989年に25haの圃場整備が完了しながらも、担い手不足が続いていた三重県いなべ市藤原町古田地区は、自作農家が少なく、整備できた圃場の管理委託要望が多くて、地区の水田を守るため、自身がほぼすべてを出資する有限会社を設立し、古田地区農家組合が農地利用調整を担い,藤原ファームが作業を受託する二階建て集落営農の体制を築いた。88歳の現在でも、古田地区の水田風景を次世代に継承するための方策を第一線で検討している。
代表を務める「ほうすけクラブ」は2005年に毎日新聞社「グリーンツーリズム大賞2004」大賞を受賞した。また、古田地区は2017年に農林水産省優良賞を受賞した。
このほか、2011年に三重地域資源活用“お見事”企業グランプリ最優秀賞受賞、2014年に三重県産業功労者表彰受章、2015年に毎日新聞社第45回毎日農業記録賞優良賞受賞、など。
近藤氏の取り組みを取り上げた書籍として、佐藤奨平編著『和菓子企業の原料調達と地域回帰』(筑波書房、2019年)がある。


- 1 ■山村地域は農地の価値が減ってきている
- 2 ■工場があっても、本社が東京にあると東京で税金を納めちゃう
- 3 ■一生懸命働いている都会の人が、こういう田舎に来ても、田舎の人が自然の美しさを保っておれば、それによって週末田舎に来て、いやされる日本であるべきだと思います。
- 4 ■農水省としてはやはり農地を守ろうとする。でも守るのは農家やね。その農家が経営の上で、農地を守るのは大変
- 5 ■やっぱり、リモートは味気ないところがある
- 6 ■農地は捨てたらいかんと思うのだけども。その守るのに、どうして守るかというのを88歳でも考えとる。まだ止まれん、前見て行かなあかん、というのはそこにあるね
- 7 ■経営理念というのは、ぶれたらあかんね。方法は、色々変えていかなだめだし。
- 8 ■農地に愛着をどうやって持たすか
- 9 ■木を切って売って、嫁入り道具を買っていた時代
- 10 ■スマート農業というと、やっぱり、3000平米以上じゃないとだめだし、
- 11 ■農地をどういうふうに国が維持をするのか、捨てるのか。どうするのかという、個人ではできん大きな問題を考えもらわないと
- 12 ■そんな6次産業も、ままごとや、産業なら1億円以上、少なくても売上げするのだ。そういうものに対して、補助や支援をしないことにはあかん。
- 13 ■予算を何に使うかの振り分けを、省内でやるわけやろうな。それに対して、やっぱり、日本農業の研究所とか、いろいろな人方の意見が出ていってくれなあかん
- 14 ■健康でおるためには、結局、きれいな食べ物というか、添加物の入らない、農薬を使わない食べ物をね
■山村地域は農地の価値が減ってきている
――農業観や農地観についてお伺いしたいのですが、いかがでしょうか?
近藤:私の考え方はね……昭和9年に生まれて、戦前戦後から食糧不足で、先祖が開墾して作った農地を大事にせなあかんという精神が、農家にはどこにもあったわけです。それで、まだ、足りないと、どんどん開墾していって増やしたけれども、ところが時代とともにそれが重荷になってきました。ものの考え方が変わってきましたからね。
――ものの考え方が変わってきた、というのはどのような?
近藤:外で働いてお金をもらったほうがいい、という時代に変わってきたわけですね。
戦後の農地改革で、もともとは大地主の農地を小作に分けたのです。それで、大地主の持分は1haと言う制限があって、あとの農地は全部、小作に安く売渡たし分散したのです。
――小作人に土地が分かれていくわけですよね。
近藤:そうそう。ところが戦後経済成長と共に、食生活に変化が出て、米余りの時代が来たのです。今度は圃場整備をして管理しやすくし、集落営農によって能率化するために、農地を集めようとしてきたのです。
ところが先ほど申し上げたように今、私が百姓採算合わないでやめたと言ったら、今まで農家だった人が出来るかというとできないでしょ、鍬や鎌ではもうできないから、トラクターとかコンバインとかいう大型の機械を何も持っとらんでしょう。
――集落営農が続かない場合に、地主の人にはもう稲作の機械がないのでどうしようもないということですね?
近藤:45戸くらいの集落ではどこでも一緒ですけれども、みなさんが百姓しておったわけ。ところが、田んぼは良くなったけれども、今度はもう百姓が出来ない。それで、今の若い人の気持ちは、「どうすんのや」、と言ったら、「それは放っとくわ」、という考え。
――なるほど。
近藤:だから、田んぼの価値が減っておるわけ。たとえば、500万円で買った車は、車庫に入れて、きちっと洗ってという感じがするけれども。2000円、3000円のものなら、その辺に放っておくのと一緒で。農地の価値が減ってきているわけです。
それで、都市近郊では宅地になるわけですし、又野菜作っていても近くで売れるので良いのですが。田舎ではそうは行かないので、先のような考え方が進んでいくと思いますね。