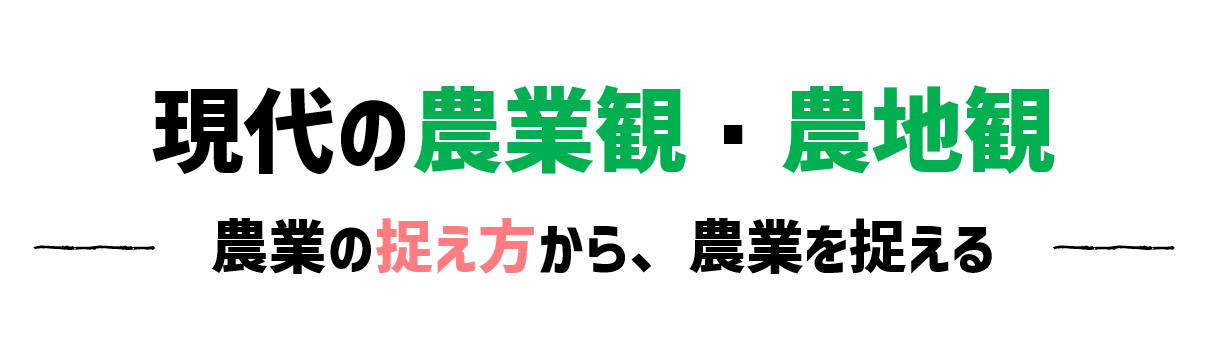太田 和彦 氏
1985年生まれ。
南山大学総合政策学部准教授。
環境倫理学、食農倫理学、風土論、持続可能な社会への移行/転換(Sustainability transition)などのテーマを扱う。2013年、東京農工大学大学院連合農学研究科修了。総合地球環境学研究所FEASTプロジェクト研究員、同助教を経て、2021年4月より現職。
主著として、訳書『食農倫理学の長い旅―〈食べる〉のどこに倫理はあるのか』(ポール・B・トンプソン著、勁草書房、2021年)、訳書『〈土〉という精神―アメリカの環境倫理と農業』(ポール・B・トンプソン著、農林統計出版、2017年)。共著として、『生活圏を学ぶアプローチ―京都府立洛北高等学校SSH課題研究における総合地球環境学研究所との共創―』(総合地球環境学研究所、2019年)。分担執筆として、Agricultural Ethics in East Asian Perspective: A Transpacific Dialogue(Springer、2018年)、『フードスタディーズ・ガイドブック』(ナカニシヤ出版、2019年)、『環境倫理学(3STEPシリーズ)』(昭和堂、2020年)、『環境問題を解く:ひらかれた協働研究のすすめ』(かもがわ出版、2021年)。
このほか講演多数。制作物として、「都市のフードポリシー・スターターキット」(https://researchmap.jp/otakazu/works/32598728)など。
――農業観・農地観というと硬い感じがしますが、ぼんやりとしたイメージでもいいので、何かありますか? こちらから最初に質問をいくつか投げたほうがやりやすければ、それでもよいですが……
太田:どの枠でお話するのが良いですか?
――「枠」というのはスタンスのようなものですよね。お任せしますし、「枠」を決めない、ということでも良いです。
太田:では、ひとまず「枠」を決めないで話そうと思います。さっそくですが、小川さんはなぜ農業観・農地観に関心を持たれたのですか? という逆質問から始めて良いでしょうか(笑)
――逆質問からとは予想していませんでした(笑)逆質問されたのは、この企画を始めて初めてです。
私が農業観・農地観に関心を持った理由は、大きく2つあって、まず1つ目は、大雑把に言えば、有名な大学の先生が「良い農業とはこういうものだ」、「良い農地とはこういうものだ」と言うからそうなのかという時代はもう既に終わっているという認識があります。2つ目の理由として、農業や農地のあり方が、個人の農業観とか農地観に大きく左右されるのではないか、と思ったからです。
2つ目の理由については、たとえばコロナ禍の中で、自分はこういう農業をやりたいけどコロナのせいでできないという状況ってあるじゃないですか。こういう作物を作りたいと思っていたけどコロナのせいで作れない、あるいは作っても売れない状態がある。これまでの研究や雑誌は、農家がなにを作っているか、なにを売っているかという結果の部分にもっとも注目して、その紹介をした後で、「この背景には農家のこういう思いがありました」と背景となる個人の農業観・農地観にふれることが多いと思うんですが、逆にするべきなんじゃないかと思っています。
先日もある農家の方と話したのですが、「農家を紹介するとき、シンポジウムとかで農家の人が話すときに、まず畑何ヘクタールとか、牛何頭とか、野菜何アールとか、その内訳はレタスが何割だとかそういう紹介をされるけれども、それに併せて、その人が農業を通じてなにをしたいか、というのも同じように並んでいいよね」という話をされていて、確かにそうだなと思いましたね。
研究者や行政担当者、マスコミなど、数字で把握したがる方が多数派ですけれど、数字に反映されない側面、つまり農業観・農地観の重要性に着目しています。農業の専門家だけでなく、全然農業に関係ない人でも、いま農業についてどう考えているかというイメージが今の農業を形作っている所もあるんじゃないかと。
最近では、熱海で土砂崩れがありましたよね。あそこは農地ではなく、山だと思いますが、ああいうニュースをテレビで見ると、普段そういったことに考えたことがない人も、一瞬、土とか山とか、林とか考えるじゃないですか。あと、東日本大震災のときに田んぼが津波に遭うところとか、新幹線に乗っていてぼーっと横を見ていたら田んぼが広がっているとか……あっ、熱海や東日本大震災の例は災害ですから、まず何より人命への心配や不安が大きいため、ぼーっと見ている景色と一緒にして例に並べてしまうのは不謹慎な例となってしまいましたが、ここで私がいいたいのは、思いがけないというか、無意識というような状態、準備していないような状態で認識されている農業や農地の姿なんですよね。専門家か否かにかかわらず、普段、農業とか関係ない人でも、そういうときに感じられるものを拾い集めたいな、と思っています。
太田:なるほど。1番目の理由は、いわゆる農地観・農業観が一律のものではないよね、というお話ですね。農地は単純に農産物を生産する以外にも、そのイメージや文化的シンボルとしての側面、周囲の生態系との関わりなどの側面があり、どれをどのような背景で強調するかによって、農地の位置づけは変わってきます。
たとえば、カナダのある都市では、カナダに移住してきた移民の方の孤立を防ぐために、地元の方と一緒に農地を耕すというプログラムがあると聞きました。移住してきた人が、地域のコミュニティで一緒に農作業をしながら、いろいろ情報交換したり、人のネットワークを作っていくという取り組みです。もちろん、全員参加ではなく、やりたい人がやってくださいね、という感じらしいです。
いずれにしても、都市の中の農業の役割は、必ずしも生産物の供給ではなくて、人と人の間の紐帯となることが期待されている。
2番目の理由は、生産者はもちろん、生産者ではない人もどのように農業をイメージしているか、どのように語っているかが、農業のじっさいのあり方に与えている影響についてでした。
生産者ではない人がこのなかに入るのは重要だと思います。都市人口も世界の半分は都市に住んでますし、農業に直接関わっていない人のほうがこれからも圧倒的に多くなりますから。そのなかで、いろいろな農地観・農業観を集めるのが小川さんの今回の狙いと。
――研究者だと、なかなか農業観・農地観を語れないですよね。
太田:語れないというか、たぶん私の農業観・農地観は語っても面白いものにはならないと思うので……。実際のところ、私自身は農作業をしているわけではないし、土壌の研究はちょっとかじってはいるので知ったようなことは言えます。
たとえば、「アグロエコロジーのように、社会と生態系と調和した農業が重要です」とか、「土壌微生物は、肉眼ではほとんど見えませんが、見えないところにも目を配った農業のあり方が、今後は重要になると思います」みたいな。
「食農倫理学の研究者」の枠であれば、そういう話をすると思います。ただ、それを私自身の農業観・農地観として話せばよいかというと、たぶん違うんですよね。
つまり、農業観・農地観といったときに、そのもとで何をするのか、何をしたいのか、というのが私はそんなにないんですよ。
なにかしらの農業観・農地観が次のアクションに結びつくというのは、地に足がついていて面白いと思います。たとえばレストランを経営されている方が、自分で畑を作るとか、あるいは運送業をやられている方が、小規模農家のための特別バリューパックみたいなものを作るとか。
そういう場合、農業観・農地観は、現場で具体的に試され、彫琢されていく機会がありますが――つまり、思い通りにならなかったり、想定外の派生効果が生じたりして、現実がその方の農業観・農地観を常に裏切っていくという場面に立つことがあると思うのですが――、私はそういう彫琢の機会をあまり持っていません。
■農業・農地の望ましいあり方について話せる場を開くことを「食農倫理学」は重視する
――なるほど。それでは、「食農倫理学の研究者」の枠から、まずはお話をうかがってもよいですか?
太田:食農倫理学(food ethics)は、食べることに関わるさまざまな悩ましい問題を扱う分野です。その観点からお話するとすれば、たとえば「手間はかかるが、環境負荷が少ない農法」があったときに、農業が本当に好きな専業農家の方はそれで良いと思うんですが、兼業農家の方や高齢農家の方には必ずしもマッチしないでしょう。
また、いま私たちが安価な食材を安定して得られるのは、認めたくないですが、浪費の激しい大量生産・大量流通のシステムのおかげです。農業と農地の持続可能性を向上させるために、農作物の値段が多少高くなることを受け入れることができる人もいますが、その価格の変化で本当に食費に事欠く人もいるでしょう。
しかし、もちろんいまのままのフードシステムでは、増加する人口を養うことは不可能です。
ここでのポイントは、私たちはある側面に注意を向けるとき、同時に他のある側面への注意を不可避に欠く、という点です。
土地倫理であったり、スチュワードシップであったり、世代間倫理であったり、私たちはいろんなレンズを使って、農業や農地の望ましいあり方について検討することができますが、万能のレンズというものはありません。
だからこそ、今回のこのインタビューのように、ときには矛盾するような複数の側面から農業や農地を見て、話し合うという対話の場が必要になります。「手間がかかっても、生態系への負荷をできるだけかけないような農業に移行していくべきだ」という人と、「安価で栄養のある食べ物を誰でも得られるべきだ」という人が同じテーブルについて交渉を始められるようにすることが、ここでの課題となります。
小川さん(聞き手)がお話されていた、いろいろな農地観・農業観を集めたいと思っている2番目の理由とも重なると思うんですが、相手の意見に対して、いきなり賛成/反対の意見表明をして、その詳細に耳を貸さなくなるということを避けるうえでも、自分とは違う「望ましいあり方」を描いている人が、どのような仕方でその見方を養っていったかをあらかじめ知っておくことは重要だと思います。フードシステムにはいろいろな人が携わっており、その複雑さゆえに成り立っています。
 図1「都市のフードポリシー・スターターキット:関係する人々や組織」(制作:Bowlgraphics)
図1「都市のフードポリシー・スターターキット:関係する人々や組織」(制作:Bowlgraphics)――なるほど。少し話は変わるのですが、2021年6月に『水田フル活用の統計データブック』(三恵社)という本を刊行しました。
そこで取り上げたのが日本の水田政策です。いま、各地域で「水田フル活用ビジョン」(現、水田収益力強化ビジョン)を作り、それにもとづいて補助金を使っていきましょうという取り組みがなされているので、それをまとめました。このビジョンなのですが、良い事例もある一方で、骨抜きになっている部分も多いのではと思っています。その原因は、一つには、ビジョンというものの扱い方を教わってないからだと思うんですよね。
「水田フル活用ビジョン」は、毎年、県や地域の行政やJAなどの関係主体で作っているのですが、ビジョンを作るってそんなに簡単なものではないと思うんですよね。
それに輪をかけて、国会の予算が3月末に決まるじゃないですか。だから、春から地域の田んぼをどう使うかということを6月末までにビジョンとして策定して提出するんですよ。しかも担当者も異動するじゃないですか。なので、大体そんなに練られてないんですよね。
もちろん、ちゃんとやっているところはやっているんですが。だんだん国の縛りとか要件も多くなっていって、こういうルール入れてください、とかなっているのを見て、話し合うとかって現実的に無理なんじゃないかなと思ったりしています。そういったビジョン作りや、主体間の関係性を育む、共通了解を高めるようなプログラムに、食農倫理学は関わりますか?
太田:とても関わると思います。ただ、ビジョン作りなどの具体的なプログラムを作るうえでは、別の仕掛けがいると思います。国内外で注目されているのは、演劇、アート、そしてゲームを用いたアプローチです。私が所属していた地球研のFEASTプロジェクトでは、京都のNPOや有機農業をされている方と一緒にロールプレイを行ったり、気候変動の度合などで分けられた4つのシナリオに対応する「未来の給食」を展示して、来場者の意見を募ったりなど、いくつかの試みをしています(*1)。
特にロールプレイは、運営側が、参加者にうまく集中してもらえるように演出できるかどうかにかかっているところが大きいのですが、とても効果が大きいと思います。例えば、水田フル活用ビジョンを考えるうえで、30分だけ「Iターンでこの地域にやってきた移住者」として話してください、あるいは「億万長者」「市長」「30年後の未来からやってきた人」「引きこもっている人」として話してください、と役割を振って、テレビ番組の『笑点』の大喜利のようにちょっとした小道具をつけて議論をしてもらうと、それまで自明と考えられていた枠組み――農業観・農地観を含む、自分の世界観――から、少し身を引き離したところで意見交換をすることができるようになります。
この役割は、カードに書いて、参加者にランダムに割り振られるのが良いと思います。
印象的だったのが、長年、有機農業に携わってきた「為せば成る」を座右の銘にしているような方が「ニート」の役割カードを引いたときに、ちゃんと都市計画をグループで検討するセッションの中で、「俺はもう何もやる気が起きないんだよ、放っておいてくれ」とちゃんとニート役をやってくれた後で、とても新鮮な体験で視野が広がった、と話されていたことですね。
――(笑)。それは相当な演技力が要りますよね(笑)
太田:うまくいくどうかはかなり参加者と主催者に依存すると思います(笑) あと、予備知識もいるので、万人向けの手法ではないですね。「Iターンでこの地域にやってきた移住者」がどんな期待をしているのか、どんな課題を抱えているのかを、演じる側が知っていなければ、ステレオタイプをなぞるだけになるでしょう。
――そこが難しいですよね。
太田:とはいえ、演じてみた後で、自分は「Iターンでこの地域にやってきた移住者」のことを全然知らなかったな、ということがわかれば、それで良いと思いますし、知るきっかけを提供できるというのはこの手のワークショップの良いところなのではないかと思います。
――なるほど。演技の時間が終わってから、「Iターンでこの地域にやってきた移住者」の持つ視点についての、自分が知っている事例を話し合うという仕方でコミュケーションが生まれることもあるでしょうね。ただ、やはりファシリテーターや、ワークショップを取りまとめる運営の力量がとても問われそうですよね。
太田:それは間違いないと思います。ワークショップで緊張感をとるアイスブレイクの仕方をはじめ、演劇から学べることは多いのではないかと思います。
――そういった手法は知らなかったので勉強になりました。農業観、農地観のみならずニート観、Iターン移住者観まで、自分や他者のもつ「観」を考えるきっかけ作りにもなりそうです。
地域の水田のビジョンを示す「水田フル活用ビジョン」作りも、結局、いま集まっている当事者だけで考えていることは問題なんじゃないかと僕は思っていたんですが、やりようによっては他の視点を仮想的に取り入れることもできるということですね。
■「土」と「農地」の違いとは?――「土」はヒューマンスケールを越えている
――先ほど、土壌のお話も出ていましたが、「土」と「農地」の一番大きな違いは何だと思いますか?
太田:土は必ずしも生産を企図していない、土は生産の媒質に留まるものではない、というところが一番大きいと思います。
農地において土はあくまでも生産の基盤として位置づけられますが、土は保水や炭素貯留の要であり、生物の死骸の分解がなされる物質循環の欠かせない要素です。
別の言い方をすれば、「土」はヒューマンスケールを越えている対象です。人間の生きている時間や空間のスケールにおさまらないような速度と大きさで変化が生じます。
たとえば、表土は、1センチ分厚くなるまでに、遅いところだと数百年かかります。日本は早いほうですが、それでも数十年かかります。表土の生成スピードは、人の感覚の外にあります。
また、私たちはほとんどの土壌微生物を肉眼で見ることができません。ミミズやオケラは見ることができますが、ツリガネムシとか物凄く沢山いる線虫とかは、虫眼鏡とか顕微鏡がないと見ることができません。そもそも私たちは体のサイズが大きすぎるので、モグラのように土の中に潜れない。なので私たちは土の中で何が起こっているのかを把握するのがとても苦手です。
ヒューマンスケール、私たちが自明としている時間の尺度、空間の尺度、あるいは想像力の尺度を越えたところで生じる土の動態のなかで、人間に関わるところを中心に把握し、制御したところのものが「農地」を構成する要素となるのではないでしょうか。
――なるほど。土の話でいうと、「土」という言い方もすれば「国土」という言い方もありますよね。その線引きは国境で線引きされるわけですが、国境もスケールとしては土を越えてこないというところですよね。
太田:所詮、ヒューマンが作った制度上のものですからね。
――「ヒューマンスケールを越える」ということが鍵になるのでしょうか。
太田:より正確に言えば、「ヒューマンスケールを越えたところで生じる事象についての想像力を育み、考慮できるようにする」ことです。
私たちは、時間的にも空間的にも本当に土のごく一部しか知ることができません。農地の土は酷使すると、すぐに団粒構造が崩れてしまいますが、それを見ることはできません。雨が降って、土が流れてしまったときに、ようやく気が付くことができます。土壌をうまくケアしながら使っていくためには、人間同士で使っている尺度とは違う尺度が必要になります。
■〈工場としての農地〉と〈庭園としての農地〉
太田:ヒューマンスケールという点からいえば、現在、日本の多くの人が持っている農地観って、どちらかというと工場に近いものだと思うんですよ。
――製品づくりといった感じですか?
太田:〈工場としての農地〉のイメージは、工場としての「農地」に必要な資材が投下されて、それを製品として出荷していくのが「農業」であるというものです。これと対になっているのが、〈庭園としての農地〉です。
食べられる庭としての「農地」があり、非常に狭いところに年間を通していろいろな作付けを行い、その場所に合った形で、見た目も良く、育てるのが「農業」であるというイメージです。この2つの農地観があると思います。
〈工場としての農地〉の方が、当然ですが、人間にとっての短期的な生産効率は間違いなく良いです。大量に作って大量にさばく。このシステムによって世界中の多くの都市が養われているので、これを全否定するつもりはないんですが、環境負荷を考えると、今後20年、30年と続けられるようなやり方ではない。
また、〈工場としての農地〉は土地が広いことが前提です。広い土地に大量の資源を投入するタイプじゃないと、その長所である効率性を活かせないので。そうすると、どうしても都市と農地が地理的に離れざるを得なくなってしまう。都市の周辺は地価が高いですから。
都市農業と親和的なのは、〈庭園としての農地〉です。特に日本の都市農業では、農地の、農作物を生産すること以外の機能がむしろ注目されるところが多い。
たとえば、生産緑地や、ビルの屋上などに作られている菜園は、食べられるものが沢山植わっている庭のようなものとして捉えられているのではないでしょうか。
土壌の話とも関連しますが、その場所により適した、過剰な負荷をかけない農業のあり方を考えたときには、〈工場〉より〈庭園〉として農地を見る方が理に適っていると思います。
この2つの農地観のあいだで、バランスを取りながら――バランスを取りながらって言い方は便利ですけど、なにも言っていないのに等しいですね――日本の場合は、人口減少の具合を見ながら、農地の管理をすることになるのではないかなと思います。
――都市農業と親和的なのは〈庭園としての農地〉であるというお話でしたが、それは経営が成り立つということでしょうか?
たとえば土地が高いから農地面積は限られたものにならざるをえないとか、でも購入者となる住民が多いから、限られた面積の農地でも、生産物が庭先販売されて経営的になりたつとか。
あと、都市部に緑地を残したいという都市計画上の思惑と、固定資産税を下げたいという土地所有者の思惑が重なるということもありますね。
太田:そうですね。
――この〈工場としての農地〉と〈庭園としての農地〉というのは、太田さんがどこかで聞かれたりとか、論文で書かれたものですか?
太田:アイディアの祖型は、『〈土〉という精神』や『食農倫理学の長い旅』を描かれているポール・B・トンプソンさんの論文です。
彼は、農地・農業についての観点を「工業的な見方(industrial vision)」と、「アグラリアン的な見方(agrarian vision)」に分けています。アグラリアンは日本語に訳すのが難しい語ですが、「篤農家」に近いです。
トンプソンさんの主張は、多くの人は「工業的な見方」と「アグラリアン的な見方」のどちらかしか見ていないけれども、両方の視点をとるべきだし、自分の持っていないはもう片方の観点で農地・農業を見る人の話に耳を傾けながら、自分のやるべきことを広い視野で探っていくべきだというものです。
2015年に、土壌肥料学会の国際シンポジウムでトンプソンさんが講演されたことがあるのですが、そのときの講演録(*2)がもっとも読みやすいと思います。
――太田さんは〈工場としての農地〉と〈庭園としての農地〉のバランスをとるというお話の際に、人口減少の話をされましたが、人口減少はあくまでひとつの例ということですよね?
太田:はい、そうですね。それぞれの場所において望ましい農業・農地のあり方を探るうえで、この2つの観点から検討するのはいかがでしょうか、という提案です。
いまは〈工場としての農地〉のほうが主流なので、〈庭園としての農地〉の意義を強調した言い方になりますが、両者は相補的なものだと思います。その補い方がケースバイケースで変わってくるので、あとは地道に環境調査や社会調査、話し合いを重ねて、より良いあり方を探っていくということになると思います。
たとえば、都市農業と〈庭園としての農地〉は親和的であるという話をしましたが、これはあくまでも先進国の大都市における都市農業の話です。エクアドルの首都のキトでは、4,000か所以上の都市型農地があり、農地管理者に対する研修などの支援も行われていますが、これはキトにおける都市農業の最大の目的が、低所得者向けの食料供給プログラムとして位置づけられているためです。この場合は、真剣に単位面積あたりの収量を気にしなければならないので〈工場としての農地〉としての側面を無視できなくなります。
■シリアスゲームと農地観・農業観――気軽に、楽しく、さまざまな農地観・農業観にふれることができる
――太田さんは、社会問題や環境問題をテーマにした「シリアスゲーム」と呼ばれるゲームについての研究にも携わられていますが、最後にシリアスゲームについてもお話しただけますか?
太田:「水田フル活用ビジョン」についてのお話のところで、ビジョン作りなどの具体的なプログラムを作るためのアプローチとして、演劇、アート、そしてゲームをあげました。
このなかでゲームは、参加者がシミュレーションや特定のルールを通じて気軽に試行錯誤や意見交換できるという特徴があります。ゲームプレイを通じてシミュレーションをしたり、状況に応じた対応を議論する機会を得たりすることができます。
シミュレーションであればデジタルゲームが得意ですし、議論の機会を作るのであればボードゲームが得意です。
さらに、複雑で手の出しようがない状況を、一度、「ルール」と「キャラクター」と「勝利条件」があるゲームとして表現することによって、理解することができるようになることもあります。
シリアスボードゲームジャムという、研究者やゲームクリエイター、学生、非営利団体や企業に勤めている方が即興でチームを組んで、シリアスゲームを作るイベントを2018年から開催しているのですが、ゲーム作りを通じて、いままで考えたこともなかった話題を調べたり、チームのメンバーと話したりして、多くの発見があったと――そして、あらためて問題の厄介さに気がついたと――いう声をいただいています。
 図2 シリアスボードゲームジャムで作られたゲーム「コモンズの悲喜劇」は農地の荒廃を防ぐためにプレイヤー同士で拠出金を出し合いながら開拓を進める必要がある(制作:藤枝侑夏、井上明人 https://tragicomedy-c.jimdofree.com/)
図2 シリアスボードゲームジャムで作られたゲーム「コモンズの悲喜劇」は農地の荒廃を防ぐためにプレイヤー同士で拠出金を出し合いながら開拓を進める必要がある(制作:藤枝侑夏、井上明人 https://tragicomedy-c.jimdofree.com/)シリアスボードゲームジャムでは、これまで連続して「食」を共通テーマにしてゲームを作っています。
17チームがそれぞれ作品を開発しましたが、ひとつもトピックが重なっている作品がありません。移住者、栄養バランス、世界の飢餓、子供の貧困、日本酒の醸造、昆虫食、コモンズの悲劇、最後の晩餐、フードロス……、これらの広がりは「食」というテーマの奥深さを感じさせるものです。
農業観・農地観の検討や掘り起こしとも関わるものなので、今後も続けていければと思っています。
(おわり)